続いて「武家・町屋ゾーン」。
住人たちが守り抜いた町並み
石見銀山は、江戸末期から産出量減に悩まされ徐々に衰退していく。
そして、昭和18(1943)年には完全閉山となり、大森のまちは著しい過疎化が進むことになる。
このままじゃいけない・・
昭和32(1957)年、「大森町文化財保存会」が発足。
家屋の保存改修などを行い、市と連携しながら町並みを守ってきたという。
代官所や裁判所も解体の危機に瀕したそうだが、そのたびに住人たちが保存を願い、それぞれ「石見銀山資料館」「町並み交流センター」に生まれ変わった。
それらの確かな取り組みが重伝建の登録につながったことは明白であろう。
不思議なもので、まちが魅力を取り戻すと地元に残る若者、都会から移住してくる若者が増え、若い力が柔軟な発想や新しい風を吹き込むシナジー効果が生まれていく。
そんな、過疎にあえぐ地方都市のロールモデルになりそうな解がここ大森にはある。
ちなみに、石見銀山が世界遺産に登録された理由のひとつに産業遺産が自然と共存している「環境との共生」という点がある。
まちを愛する気持ちを持ち、同じベクトルを向いていれば出身がどこだろうと関係ないということ。
– 地元民と移住者の共生 –
とかくよそ者を排除し、移住者との軋轢が絶えない田舎のまちが最も見習われなければいけないのがこの点ではないだろうか。
大森のまちを歩いていて妙に心地よかったのは、そのあたりが理由だったのかもしれない。
体面や外聞にこだわるあまり何かを無理に取り繕ったり、政治的な理由で本心に嘘をつき通さなければいけなかったり、共同体であり有機体である「まち」にはこういうジレンマが常につきまとう。
みんな仲良く楽しく愉快に、そうやって毎日笑顔で生きられればどんなに幸せだろう。
そんな理想郷みたいな「まち」が存在するのかわからないが、もしあればきっと喜んで移住するだろうな、とそんなことを思ったりする。
旧河島家住宅
話が脇道にそれまくったので戻そう。
武家屋敷の「旧河島家住宅」。
確かここ、熊谷家住宅とセットで安くなるから、と勧められたんだったと思う。
代官所の地役人(地元に住んでる武士のこと)だった河島家の屋敷で、建てられたのは1800年初頭とのこと。
配置や間取りが武家屋敷の特徴をよく残しており、空気感からは武士の暮らしぶりが伺える。
武家屋敷としては唯一一般公開されている建物なので、是非熊谷家住宅とセットで見学するのをオススメしたいところ。
ちなみにこの河島家住宅も平成2年から2年に渡って修復工事を行い、塀と庭を復旧したそうな。
厨子二階から一階を見下ろす。階段がめちゃめちゃ急なので転げ落ちないように注意されたし。
大森地区は、武家屋敷や町屋、商家がごちゃっと集まった渾然としたまちなみになっており、これもまた先述した「共生」をよく現していると思う。
※だいたい商人町、武家町みたいに分かれていることが多い
これが「町並み交流センター」に生まれ変わった旧大森区裁判所。
明治23年に開所したという洋風建築はひときわ異彩を放っている。
以上、ざっくりと大森の町並みを歩いてきた。
世界遺産や銀山について詳しく知りたい方は、少し離れたところにある「石見銀山世界遺産センター」に行ったり、ガイドさんによるツアーを申し込まれるとよいと思う。
最後に行き方について。
車の場合は世界遺産センターに駐車後、パークアンドライドで大森地区へ。
電車の場合は大田市駅か仁万駅から路線バスに乗車。前者のほうが本数が多い。
どう見てもサザエのつぼ焼きにしか見えない石見銀山公式キャラクター、らとちゃん。
※「らとちゃん」はサザエのつぼ焼きではありません。
とご丁寧に否定している理由については、現地で確かめていただければ。
[訪問日:2017年8月13日]

















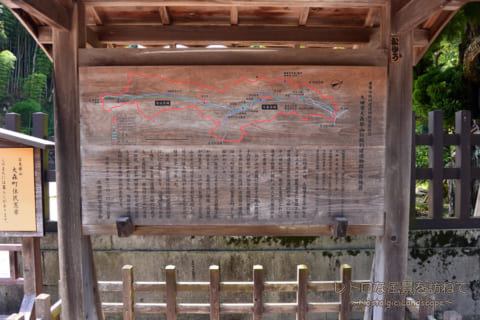




コメント